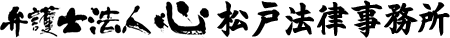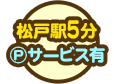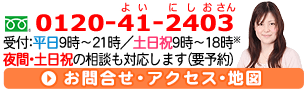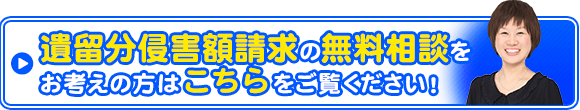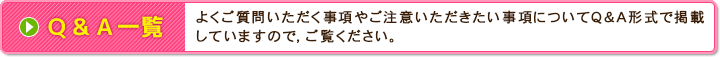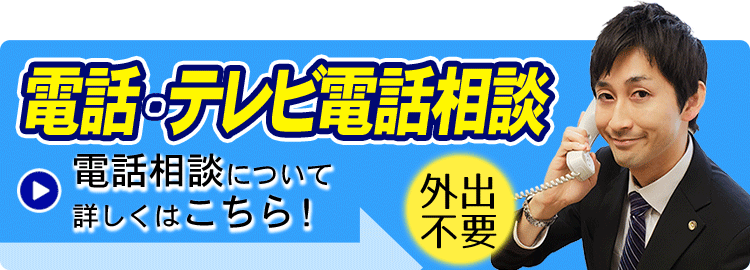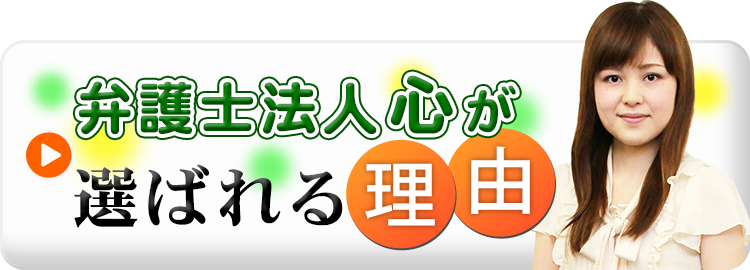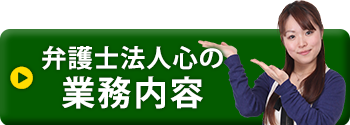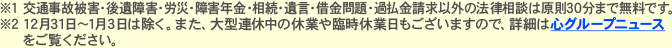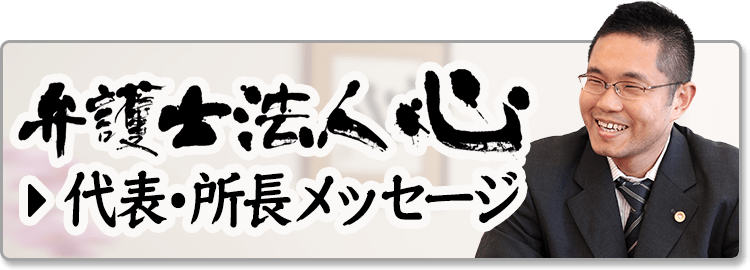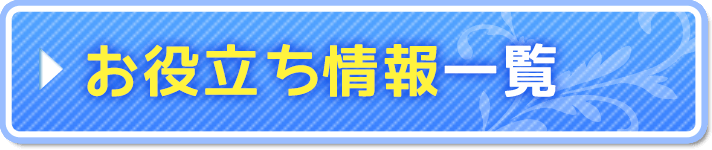遺留分を請求する際の流れ
1 遺留分とは
遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、最低限取得できることが保障されている持分的な利益のことをいいます。
民法は、被相続人が有してた相続財産について一定の割合の遺留分を取得できることを制度として保障しています。
遺留分は、主に遺言書が存在するケースにおいて問題となります。
遺留分権利者は、相続人のうち、被相続人の配偶者、子、父母までとなります。
他方で、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
具体的には、被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、被相続人の孫が代襲相続人となりますが、代襲相続人である孫も遺留分権利者になります。
被相続人の父母の両方が被相続人よりも先に亡くなっている場合も、(存命であれば)被相続人の祖父母が相続人となりますが、このような祖父母も遺留分権利者になります。
また、被相続人の子がいないまたは死亡しているけれども代襲相続人も存在せず、さらに被相続人の父母や祖父母も存命ではない場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるとされていますが、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者にはなりません。
遺留分の割合は、法定相続分によって異なります。
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子は2人いるので、子の法定相続分はそれぞれ4分の1(子の法定相続分2分の1×2分の1)となります。
遺留分の割合は、配偶者が4分の1(2分の1×法定相続分4分の1)、子は8分の1(2分の1×法定相続分4分の1)となります。
遺留分権利者から権利譲渡を受けた人や遺留分権利者から相続した人も、原則として新たに遺留分権利者になることができます。
2 遺留分を請求するにあたって
遺留分の請求は、相続発生後いつでもできるというわけではありません。
遺留分を請求できることを知ってから、1年以内に請求を行う必要があります。
法律上は、遺留分の請求の方法は定められていないため、口頭で遺留分の請求をする意思を伝えるだけでもよいとされていますが、後になって、「遺留分の請求を受けていない」と主張されてしまうと、遺留分の請求が認められなくなってしまう可能性があります。
そこで、遺留分の請求を期限内にしたことの証拠を残すために、内容証明郵便で、遺留分を請求する意思表示をするのが一般的です。
次に、遺留分について交渉を始めるにあたり、請求金額を確定させる必要がありますが、遺留分の金額を決めるためには相続人の人数の確定と、相続財産の調査が必要になります。
相手方の協力が得られない場合は、請求する側で調査をしなければならず、時間がかかります。
相続財産調査をしている間に、遺留分の期限が過ぎてしまうことがあるので、先に遺留分を請求する意思表示をすることが重要です。
遺留分を算定する対象となる財産には、①被相続人が相続開始の時において有した財産、②相続開始前1年以内に贈与した財産、③債務の全額、④過大な死亡保険金があります。
① 被相続人が相続開始の時において有した財産
相続財産には、不動産や預貯金、有価証券等があります。
また、相続財産には、自動車や貴金属類等の一般的に経済的価値があると判断される財産も含まれます。
② 相続開始前1年以内に贈与した財産
相続開始前1年以内に、被相続人から相続人及び第三者に対して贈与された財産についても、遺留分の算定対象となる財産に含まれるのが原則です。
ただし、被相続人から相続人に対して行われた贈与で特別受益(「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」)に該当する贈与については、例外的に10年前に行われた贈与までさかのぼることができます。
例外の例外として、第三者に対して行われた贈与であっても、被相続人と第三者の双方が「遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき」は1年前の以前に遡って遺留分の対象とできる点に注意が必要です。
③ 債務の全額
被相続人が債務を負っていた場合には、「被相続人が相続開始の時において有した財産」及び「相続開始前1年以内に贈与した財産」から債務の全額を控除する必要があります。
そのため、遺留分の主張を行う際には、どのような債務が存在していたのかを明確にする必要があります。
この時、葬儀費用が債務に該当するかどうかが問題となることが多いですが、葬儀費用は喪主が負担するべきであると考えられているため、原則として債務の計算に含まれませんので注意が必要です。
④ 過大な死亡保険金
死亡保険金は、被相続人の死亡によって生命保険受取人が直接受け取ることができる受取人固有の財産であり、相続財産に該当しないのが原則とされています。
ただ、生命保険を契約すれば遺留分を0にできるとすると、遺留分権利者にとってあまりにも酷な結果となってしまうため、相続財産と比較して過大な死亡保険金が支払われている場合には、相続財産に持ち戻すことが認められる可能性があります。
このとき、過大な死亡保険金といえるのかが問題となりますが、受取人である相続人と被相続人の関係、介護等による被相続人への貢献の有無等の様々な要素を考慮して総合的に判断されています。
一般的な目安としては、死亡保険金が相続財産の価格の50%を超えている場合には過大と評価される傾向にあると思われます。
3 遺留分侵害額請求調停の手続き
交渉で合意ができない場合は、調停前置主義が取られているため、遺留分侵害額請求調停を提起するのが原則です。
⑴ 申立人
遺留分侵害額請求調停を提起することができる人は以下のとおりです。
① 遺留分を侵害された方(兄弟姉妹以外の相続人)
② 遺留分を侵害された方の承継者(相続人、相続分を譲り受けた者)
⑵ 申立先
遺留分侵害額請求調停を提起する裁判所は法律で決まっています。
① 相手方の住所地の家庭裁判所
② 当事者が合意で定める家庭裁判所
⑶ 申立て費用
調停の申立てを行う際に、家庭裁判所に対して収入印紙の納付と予納郵券(相手方への書類の郵送に使用する切手)の提出を行います。
① 収入印紙1200円
② 予納郵券(各家庭裁判所によって微妙に金額が異なります。)
⑷ 必要書類
申立てを行う場合には、以下に記載する書類を家庭裁判所に対して提出する必要があります。
① 申立書 3通
裁判所の定める書式を活用して申立書を作成していきます。
申立書は、相手方に送付される資料になりますので、裁判所用、相手方用、申立人控え用の3通を提出することになります。
この時に提出する相続財産目録には、被相続人の相続財産を記載していくためどの財産がどこに所在しているのか等を正確に記載していく必要があります。
② 送達場所等届出書 1通
③ 進行に関する照会回答書 1通
裁判所の定める書式を活用して照会回答書を作成していきます。
この時に、これまでの交渉経緯等について記載していくため、ご自身に不利な事実の記載を行っていないかの確認が必要です。
④ 相続人全員の戸籍等謄本(全部事項証明書) 1通
取得から3か月以内のものが必要です。
⑤ 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(全部事項証明書・除籍、改製原戸籍謄本等) 各1通
取得から3か月以内のものが必要です。
⑥ 相続財産目録 1通
⑦ 不動産登記事項証明書 各1通
相続財産に不動産がある場合、取得から3か月以内のものが必要です。
⑧ 公正証書遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写し 1通
⑸ 調停の進行について
家庭裁判所に申立てを行った後には、家庭裁判所から期日の指定が行われます。
指定された期日までに、遺留分に関して主張したい点等があれば、事情説明書を作成して、ご自身の主張を書面として提出する必要があります。
また、必要に応じて証拠資料の収集、作成を行う必要があります。
調停は、裁判所を介した話し合いですので、話し合いが難航し、調停が不調に終わることもあります。
その場合は、地方裁判所に、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。
4 遺留分侵害額請求訴訟の手続き
遺留分侵害額請求訴訟においては、裁判所が訴訟の当事者が主張している事実を証拠に基づいて判断をします。
そのため、訴訟の当事者は、自分に有利な証拠を集めること重要となります。
当事者双方の主張立証が尽くされた時点で、裁判所が双方に和解ができるかどうか打診をすることが一般的です。
和解が成立すれば、事件は解決しますが、和解がまとまらない場合は、裁判所が判決を言い渡します。
裁判所が下した判決にも不服がある当事者は控訴をすることができます。
判決を下した裁判所よりも上級の裁判所(控訴審)が、新たに審理・判決をすることになります。
控訴審の判決にも不服がある当事者は、更に上告を行い、これが認められれば、控訴審よりも上級の裁判所(上告審)が新たに審理・判決をすることになります。